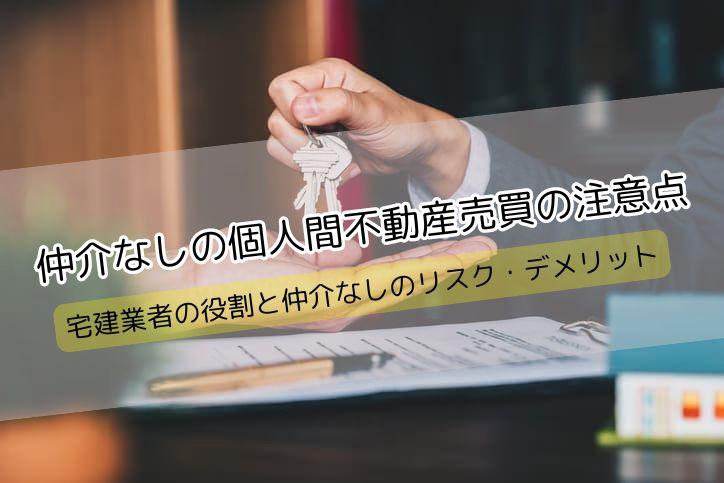土地の売却では、仲介手数料などの諸費用がかかります。
諸費用について理解しておかないと、思わぬ出費で手元に残るお金が少なくなりかねません。
ただ、費用の中には控除などで抑えられるものもあるため、それらを節約する方法まで理解しておくことが重要です。
この記事では、土地売却にかかる諸費用や、費用を抑える方法について、分かりやすく解説します。
土地売却にかかる費用や手数料・税金の種類
土地売却では、以下のような費用や手数料・税金がかかります。
- 仲介手数料
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 登録免許税(司法書士報酬)
- その他
仲介手数料
仲介で売却した場合、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
土地の売却方法には、不動産会社が買主を探して契約までサポートする「仲介」、不動産会社が買主となる「買取」、不動産会社を挟まず個人でやり取りする「個人間売買」があります。
仲介手数料が発生するのは、これらのうち「仲介」での売却のみです。
一般的な土地売却では、ほとんどのケースが仲介での売却となります。
仲介手数料の額は後ほど詳しく解説しますが、100万円を超えるケースも少なくないので、計算方法を押さえ、資金計画を立てておくことが重要です。
譲渡所得税
土地を売却した利益は「譲渡所得」と呼ばれ、所得税・住民税、また、2037年までは復興特別所得税の対象となります。
この譲渡所得にかかる税金は、総称して「譲渡所得税」と呼ばれます。
譲渡所得税の税率は、土地の所有期間に応じて20.315%または39.63%のいずれかです。
高い税率の方で課税されると税負担も高額になるので、課税額についても理解しておくようにしましょう。
譲渡所得税については後ほど詳しく解説するので、参考にしてください。
なお、譲渡所得税が課税さ��れる場合、確定申告が必要になります。
一方、売却で利益が出ていない場合(売却損)は、譲渡所得税は課税されません。
印紙税
印紙税とは、契約書や領収書などの一定の書類を作成する際にかかる税金です。
土地売却の場合は、売買契約書が印紙税の対象となります。
印紙税は、契約書に記載されている金額(売却額)に応じた収入印紙を貼付・消印することで納税したとみなされます。そのため、契約書には貼付・消印もれがないように注意しましょう。
一般的な土地取引の価格帯での税額は、以下の通りです。
| 契約金額 | 本則税額 | 軽減後の税額 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
印紙税は2027年3月31日までは、軽減措置が適用されます。
印紙税は納税を怠ると、過怠税として本来の税額の3倍額相当を徴収されるペナルティがあるので注意しましょう。
登録免許税(司法書士報酬)
登録免許税とは、不動産登記の際に法務局に支払う手数料的な税金です。
土地売却では、主に以下のような不動産登記が関わってきます。
- 抵当権抹消登記
- 所有権移転登記
また、売却後には所有者を売主から買主に移転する所有権移転登記を行うことにな�ります。
所有権移転登記の費用は買主が負担するのが一般的なので、売主に登録免許税の負担は無い契約内容にする場合が多いです。
とはいえ、どちらが負担するかは合意で決まるので、事前に確認するようにしましょう。
売主が主に負担するのは、抵当権抹消登記にかかる費用です。
ローンを利用していない土地の売却の場合、抵当権抹消登記は必要ないため、このお金もかかりません。
抵当権抹消登記の登録免許税は「不動産個数×1,000円」です。土地1筆なら1,000円、土地+建物なら2,000円の税負担となります。
なお、不動産登記手続きは自分でも行えますが、決済時に同席する司法書士に依頼するのが一般的です。
とくに、売却と同時に抵当権抹消登記する場合は、金融機関が手続きミスの無いように司法書士への依頼を必須とするケースも少なくないので注意しましょう。
司法書士に依頼する場合は、別途司法書士報酬が必要です。
依頼する司法書士や内容によっても費用は異なりますが、抵当権抹消登記の場合1.3万円~1.8万円ほどが目安となります。
その他
売却の状況に応じて、以下のような費用がかかるケースもあります。
| 項目 | 費用の目安 |
| 解体費用 | 【木造】3~4万円/1坪 |
| 測量費用 | 10~60万円 |
| 地盤調査費用 | 5~10万円 |
境界が確定してない土地の場合、基本的に売却前の境界確定が必要になるため、測量費が必要です。
土地の境界は法務局で取得できる地積測量図で確認可能で、登録されていない場合は取引する土地の面積が正確に示すことができないため、後のトラブルやリスクを避けて購入しない人がほとんどです。
また、土地に築年数の古い建物が建っている場合、そのままでは売却しにくいので解体して売却するケースも少なくありません。
売却前の解体であれば売主が費用を負担するため、解体費用も必要です。
地盤調査は基本的に購入後に買主が行うケースが一般的ですが、購入後の地盤調査では買主のリスクも高くなるため、売りやすくするために売主が事前に行うことも珍しくありません。
これらの費用は、土地や建物の状況や依頼先によっても大きく異なります。
そもそもこれらの費用が必要か分からない場合は先に不動産会社に相談し、実施が必要なら見積もりを取って行うようにしましょう。
土地の売却では、上記のような費用がかかります。
費用の中でも「仲介手数料」「譲渡所得税」は高額になりやすいので、内容を押さえておくことが重要です。
以下では、仲介手数料・譲渡所得税の具体的な計算方法などを解説するので参考にしてください。
仲介手数料とは
仲介手数料とは、仲介で売却した際に不動産会社に支払う手数料です。
売買契約を成立させた成功報酬として仲介会社に支払う手数料
仲介手数料は、売買契約時・決済時に不動産会社へ支払う成功報酬です。
そのため、売買契約が成立するまでは支払う必要がありません。
たとえ複数の不動産会社と契約している場合でも、売買契約が成立した取引を担当する1社にのみ支払います。
また、仲介手数料には売却活動や契約サポートなどの一連の売却までの必要経費も含まれています。
- 売買契約が成立していないのに仲介手数料を請求された
- 仲介手数料以外で費用を請求された
といったケースは違法な費用請求である可能性が高いので注意しましょう。
ただし、新聞の一面への広告を依頼したなど、通常の営業活動とは異なる営業を売主が依頼した場合は、別途費用が請求されます。
とはいえ、このようなケースは稀なため仲介手数料以外の費用請求には慎重に対応するようにしましょう。
仲介手数料の計算式
仲介手数料は、法律によって請求できる上限額が以下のように定められています。
| 売却額 | 上限額 |
| 200万円以下 | 売却額×5%+消費税 |
| 200万円超え400万円以下 | (売却額×4%+2万円)+消費税 |
| 400万円超え | (売却額×3%+6万円)+消費税 |
例えば、土地の売却額が1,000万円の場合は、1,000万円×3%+6万円で36万円(税抜)が上限です。
ただし、2024年7月1日より、売却額が800万円以下の物件では売主・買主の合意を得られれば一律30万円(税抜)が上限となっています。
これは、不動産価格が低い物件だと不動産会社側が得られる報酬が少なくなり、不動産会社がそうした物件を積極的に扱わなくなることへの対策として改正されたものです。
なお、計算式で求められる仲介手数料の額は上限額であるため、範囲内であれば自由に設定可能で、仲介手数料の割引や無料のサービスを行っている会社もあります。
しかし、ほとんどの不動産会社は上限を基準に仲介手数料を設定しているので、上限額であらかじめ費用を検討しておくと資金計画も崩れにくいでしょう。
譲渡所得税とは
土地売却では譲渡所得税が課税されるケースもあるので、計算方法を押さえておくことが重要です。
土地を売却した利益に課される税金
譲渡所得税は、土地売却の利益にかかる税金です。
大まかなイメージとしては、売却額から購入費用と売却費用を差し引いた部分が利益であり、この分がプラスなら譲渡所得税が課せられます。
反対に、費用を差し引くとマイナスになる場合は、譲渡所得税は発生しません。
また、譲渡所得税には税金控除の特例も用意されているので、利益が発生しても控除を活用して税金が発生しないケースも少なくありません。
印紙税や登録免許税は土地売却で必ずかかる税金ですが、譲渡所得税はかかるケース・かからないケースがあるので注意しましょう。
譲渡所得税が発生するケース、発生しなくても控除の特例を適用するケースでは、確定申告が必要です。
確定申告時期は売却した年の翌年2月16日から3月15日となるため、売却時期から期間が空くケースも少なくありません。
申告漏れや、売却金を全部使って納税に対応できない、などとならないように注意しましょう。
譲渡所得税を求める計算式
譲渡所得税は、以下の2ステップで計算します。
- 【課税対象譲渡所得の計算】売却額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
- 【譲渡所得税の計算】課税対象譲渡所得×税率
まずは、課税対象となる譲渡所得額を計算し��ます。
譲渡所得は、売却金から土地代や手数料などの購入にかかった費用(取得費)と仲介手数料などの売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた部分です。
また、特別控除を適用できる場合は、さらに控除分を差し引きます。
差し引いてプラスになる場合は譲渡所得税が発生するため、プラス部分に譲渡所得税の税率を乗じて税額を求めます。
譲渡所得税の税率は、以下の通りです。
| 所有期間 | 所得税 復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
所有期間5年を境に、短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分されます。
短期譲渡所得に区分されると税率も高くなるので、売却時には所有期間も考慮するようにしましょう。
土地売却時にかかる費用のシミュレーション
ここでは、いくつかのパターンで具体的に土地売却にかかる費用をシミュレーションしていきます。
なお、ここでは税金控除の特例は考慮せずに計算していきます。
通常の土地売却のケース
最初に、一般的な土地売却のケースとして、以下の条件でシミュレーションしていきましょう。
- 売却額:3,000万円
- 取得費:土地代2,000万円+その他費用200万円
- 所有期間:8年
- 建物解体なし・境界確定なし・抵当権抹消なし
上記の場合、仲介手数料・印紙税は以下の通りです。
印紙税:2万円(軽減適用なし)
譲渡費用は仲介手数料+印紙税で98万円のため、譲渡所得は以下のようになります。
利益が出ているため、以下のように譲渡所得税が課税されます。
よって、費用総額は以下の通りです。
| 項目 | 費用 |
| 仲介手数料 | 96万円(税抜) |
| 印紙税 | 2万円 |
| 譲渡所得税 | 143万円 |
| 費用合計 | 241万円 |
境界確定が済んでいないケース
次に、境界確定が済んでいないケースとして以下の条件でシミュレーションします。
- 売却額:4,000万円
- 取得費:土地代2,500万円+その他費用150万円
- 測量費用:30万円
- 所有期間:13年
- 建物解体なし・境界確定必要・抵当権抹消なし
仲介手数料と印紙税は以下のとおりです。
印紙税:2万円(軽減適用なし)
測量費�用は譲渡費用に含められるので、譲渡所得は以下のようになります。
所有期間13年なので長期譲渡所得に区分されるため、譲渡所得税は以下の通りです。
よって、費用合計は以下のようになります。
| 項目 | 費用 |
| 仲介手数料 | 126万円(税抜) |
| 印紙税 | 2万円 |
| 測量費 | 30万円 |
| 譲渡所得税 | 242万円 |
| 費用合計 | 400万円 |
売却前に家を解体するケース
最後に、売却前に建物を解体するケースとして、以下の条件でシミュレーションしてみましょう。
- 売却額:2,000万円
- 取得費:土地代1,000万円+その他費用50万円
- 解体費用:120万円
- 所有期間:10年
- 建物解体あり・境界確定なし・抵当権抹消必要(建物+土地)
- 司法書士依頼料:2万円
仲介手数料と印紙税・抵当権抹消登記費用は以下の通りです。
印紙税:2万円(軽減適用なし)
抵当権抹消登記費用:1,000円×2+2万円=2.2万円
なお、解体費用は譲渡費用に含められますが、抵当権抹消登記費用は含められないため譲渡費用は以下のようになります。
よって、譲渡所得額・譲渡所得税は以下の通りです。
譲渡所得税:762万円×20.315%=約155万円
上記の例での費用合計は以下のようになります。
| 項目 | 費用 |
| 仲介手数料 | 66万円(税抜) |
| 印紙税 | 2万円 |
| 解体費用 | 120万円 |
| 抵当権抹消登記費用 | 2.2万円 |
| 譲渡所得税 | 155万円 |
| 費用合計 | 345.2万円 |
どのような費用がかかるかは、売却ケースによって異なります。
自分の土地ではどのような費用が必要かを明確にし、費用目安を計算するようにしまし�ょう。
なお、戸建て住宅を購入して土地と建物部分を売却する場合、建物部分は減価償却して取得費を計算する必要があります。
減価償却費の計算を含めた譲渡所得税の算出方法は、下記の記事で詳しく解説しています。
▼関連記事

土地売却時の費用や手数料・税金を安く抑える方法
土地売却にかかる費用や税金は、ちょっとしたポイントを知っていることで抑えられる可能性があります。
ここでは、費用を抑える方法として以下の3つを解説します。
- 3,000万円特別控除などの特例を利用する
- 境界確定や解体は事前にすべきかよく検討する
- 信頼できる不動産会社を見つけて高値で売却する
3,000万円特別控除などの特例を利用する
譲渡所得税には、いくつかの控除の特例が用意されているので、それを適用することで税負担の軽減が見込めます。
土地売却で検討できる代表的な特例は、以下の通りです。
- 3,000万円特別控除
- 10年超所有軽減税率の特例
- 買換え特例
- 相続空き家の3,000万円特別控除
マイホームを解体して土地を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるのが「3,000万円特別控除」です。
特例が適用できる場合、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金は発生しません。
さらに、所有期間が10年を超えるケースでは譲渡所得6,000万円以下の部分の税率を引き下げられる「10年超所有軽減税率の特例」も適用可能です。
3,000万円特別控除と10年超所有軽減税率の特例は、併用できるので大きな節税効果が見込めるでしょう。
住み替えによる売却であれば、税負担を購入した新居の売却時まで繰延できる、買い替え特例が検討できます。
相続した空き家の売却なら、相続空き家の3,000万円特別控除が適用できるケースもあるでしょう。
特例によっては併用できるもの・併用できないものがあります。
また、特例ごとに細かい条件が定められているので、適用要件を確認することも大切です。
境界確定や解体は事前にすべきかよく検討する
境界確定や解体は費用も高額になってくるため、実施するかを慎重に判断することが大切です。
基本的に境界確定は必須となるケースがほとんどでしょう。
境界線が確定していない土地は、購入後に隣地の所有者とトラブルになる可能性があり、避けられやすくなってしまうからです。
不動産会社によっては境界確定が売却の条件というケースも少なくありません。
一方、解体については自身で判断するのはおすすめできません。
築年数が古い家でも安く購入してリフォームしたいというニーズも見込めます。
なかには、解体してしまうと再建築できない再建築不可物件もあるので、安易に解体することで売却が難しくなる恐れもあるのです。
解体が必要かどうかは、事前に不動産会社に相談しアドバイスをもらいながら検討することをおすすめします。
▼関連記事


信頼できる不動産会社を見つけて高値で売却する
費用を抑える方法ではないですが、売却では費用を抑えるよりも高く売却したほうが手元に残るお金を大きくできるものです。
費用を抑えることに固執するのではなく、高値での売却を目指すことを重視しましょう。
土地を高く売れるかどうかは、不動産会社の力量にも左右されてきます。
土地売却・そのエリアに強い不動産会社であれば、高値での売却も目指しやすくなるでしょう。
そのため、不動産会社を選ぶ際にはできるだけ多く査定を受けて、比較検討することが大切です。
査定額だけでなく、査定時の対応や実績・評判なども含めて総合的に比較することで、信頼でき、かつ高値で売却してくれる不動産会社に出会えるでしょう。
不動産会社の査定を比較するなら「イエウリ」がおすすめです。
一般的な一括査定サイトとは異なり、興味がある不動産会社すべてが入札する形式なので、自然と高値の査定が付きやすくなります。さらに、個人情報の入力も不要なので営業電�話の心配もありません。
土地の売却を検討しているなら、まずはイエウリでいくらで売れるか調べるところからスタートするとよいでしょう。
土地売却時の費用や手数料・税金に関するよくある質問
最後に、土地売却時の費用や手数料・税金に関するよくある質問をみていきましょう。
仲介手数料を支払うタイミングはいつ?
一般的に「売買契約時に半分・決済時に残額」か「決済時に全額」の2パターンに分かれますが、半分ずつの支払いとするケースが多いです。
ただし、不動産会社によって支払うタイミングや方法は異なるので、契約時に確認するようにしましょう。
なお、売買契約時に全額パターンは基本的におすすめできません。
売買契約後も引き渡しまで不動産会社のサポートは必要なため、すべて終わるタイミングで手数料を支払いきる方法が安心でしょう。
仲介手数料は売主と買主どちらが支払うの?
売主・買主ともにそれぞれで契約した不動産会社に支払うことになります。
売主は売却前に不動産会社と媒介契約を結びます。
また、買主も購入前に不動産会社と媒介契約を結ぶため、契約した不動産会社に支払うことになるのです。
手数料率は媒介契約を結ぶときに、前述の上限額の範囲で設定します。
売主と買主が契約する不動産会社が同一のケースと異なるケースに分かれますが、いずれであっても双方とも土地の売買代金に応じて、契約時に定めた料率の金額を支払う必要があります。
譲渡所得税を支払うタイミングはいつ?
譲渡所得税は、売却した翌年の確定申告で納税します。
確定申告時期は、売却した年の翌年2月16日から3月15日です。
申告時期に申告漏れや納税に対応できないとならないように、早めに資金計画・申告準備をするようにしましょう。
土地売却に消費税はかかる?
土地自体は非課税となるため、売却金に消費税はかかりません。
しかし、不動産会社への仲介手数料や司法書士報酬・解体などで業者に支払う費用については、消費税の対象です。
まとめ
土地売却では、以下のような費用や税金・手数料がかかります。
- 仲介手数料
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 抵当権抹消費用
- その他費用(解体費・測量費など)
なかでも、仲介手数料・譲渡所得税は高額になってくるため、計算方法を押さえておくことが大切です。
また、税金控除の特例の活用など、費用を抑える方法もあるので、上手に活用するようにしま�しょう。
費用を抑えることよりも高値で売却したほうがお得になるケースも少なくないです。
費用を抑えつつ、信頼でき高値で売却してくれる不動産会社を見つけることをおすすめします。