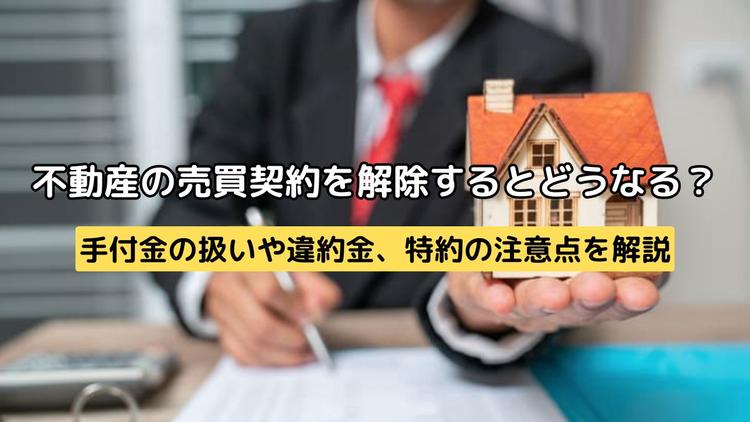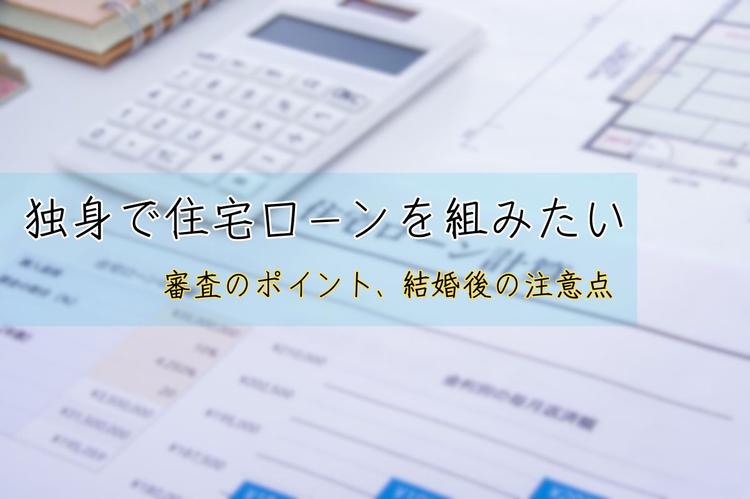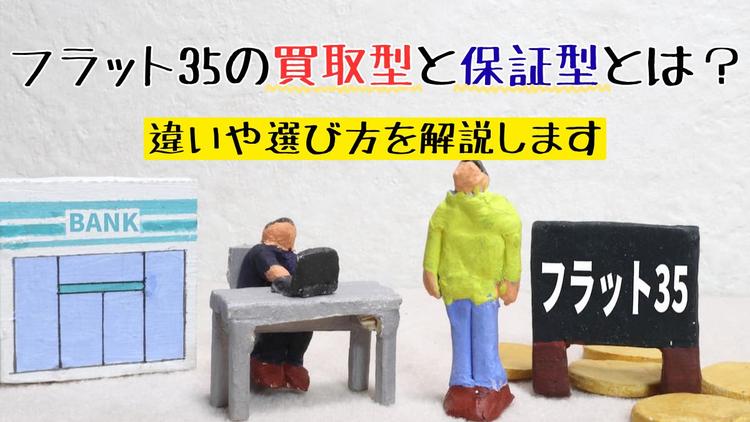農地は宅地とは異なり、厳しい用途制限が課せられた特別な土地です。
しかし、都市近郊や人気の移住地ではその価値が見直され、農家以外の人々にも注目される存在となっています。
この記事では、農家でない一般の人が農地を購入する際の条件や手続き、法律上の注意点について解説します。
農地を購入するための大前提
農地を購入したいと考えたとき、最初に理解しておくべきなのが、「農地は誰でも自由に売買できる不動産ではない」ということです。
宅地や山林とは異なり、農地には国の厳格な管理が及んでおり、その取り扱いは農地法によって厳しく制限されています。これには、日本における食料自給や農地保全という国策が深く関わっています。
まずは、一般の人が農地を買うにはどうすればいいのかを知るために、農地を購入するための大前提を押えていきましょう。
農地は「農業を行う人」のための土地
農地法第3条は、農地を売買したり貸し借りしたりする際には、原則として「農業従事者」でなければならないと定めています。
「農業従事者」とは、原則として年間150日以上農作業に従事している個人、またはそれに準じる法人などを指します。
これは、農地が不動産投資や投機の対象とされることを防ぐためであり、真に農業を行う意思と能力を持つ者だけが農地を利用できるようにするためです。
そのため、購入者に農業を行う実態や明確な計画がない場合、農地を取得する許可を得ることはほぼできません。
農業従事者になる必要がある
農地を耕作目的で取得する場合、原則として農業従事者になる必要があります。農業従事者とは、「農作業に常時従事する個人や法人で、農地を効率的に利用する意思と実績がある者」を指します。
農地法第3条では、農地の権利(所有権、賃借権など)を移転または設定する場合、当事者(権利を取得する側と移転する側)が農業委員会の許可を得なければならないと定められています。
この許可を得るためには、権利を取得する側が以下の要件を満たす必要があります。
- 全部効率利用要件: 取得する農地を含め、所有するすべての農地を効率的に耕作すると認められること。
- 農作業常時従事要件: 農作業に常時従事すると認められること(原則として年間150日以上)。
- 下限面積要件: 経営する農地の面積の合計が一定規模以上であること(地域によって異なりますが、原則50アール以上)。ただし、この要件は近年緩和・廃止される傾向にあります。
- 地域との調和要件: 周辺の農地の利用に支障がないと認められること。
これらの要件は、農地が耕作者によって有効に利用されることを目的として定められています。そのため、農地を取得して耕作を行う意思と能力がある「農業従事者」であることが求められるのです。
ただし、相続や遺贈など、一部の例外的なケースでは、農業従事者でなくても農地を取得できる場合があります。
どんな人が農地を買えるのか
「農家でなくても農地を買うことができるのか?」という疑問は、農業に関心のある都市部の人々や移住希望者の間でしばしば聞かれます。結論からいえば、「条件を満たせば可能」です。
この章では、農家ではない一般の人が農地を買うにはどうすればいいのか、具体的な条件や、どのような人が許可を受けやすいのかについて解説していきます。
農業に従事する見込みがある
農地を取得するためには、農業従事者になる必要があります。しかし、農業の経験がない一般の人でも、次の条件を満たすことで、農業従事者として農地を取得することは可能です。
- 年間150日以上農作業に従事すること
- 平日の日中に作業できる時間が確保できること
- 実現可能な営農計画があること
- 農地を適切に維持・管理できる体制があること
「農業に常時従事する者と判断されるか」という点が最も重要な判断基準となります。
「田舎暮らしがしたい」「将来使うかもしれないから確保しておきたい」など、農業そのものを目的としない購入は、原則として許可されません。
「農業の意思」を具体的に示す
一般の人が農地を取得するには、「農業をやる意思がある」だけでは不十分で、「本気度」を示すための�準備が大きく影響します。
次のような要素を整えておくと、許可が得られやすくなります。
- 営農計画を作成する……どの作物を、いつ、どの面積で栽培するか。作業体制・機械・資材・出荷の見通し。収支シミュレーション
- 農業研修を受講する……市町村・JA主催の就農セミナー、農業法人などでの実習経験、農業大学校・農業塾での研修受講
- 地元との連携……地域農家との関係性の構築、農協、普及センター、農業委員との事前面談、地元自治会とのつながり
営農計画に無理がある、農業の知識や経験が乏しい、必要な機材や作業体制の準備が不十分と判断された場合も、許可は下りません。
特に、農業未経験者が突然「大規模農業を始めたい」と申請しても、実行可能性が低いと見なされるので注意しましょう。
新規就農者としての認定を受けるという道も
農業委員会の許可を得るうえで有利になるのが、「認定新規就農者」として行政に認められることです。
「認定新規就農者制度」とは、農業を新たに始めようとする人が、市町村に「青年等就農計画」を提出し、その計画が適切であると認められることで、各種の支援措置を受けられる制度です。
正式には「青年等就農計画制度」と呼ばれ、農業経営基盤強化促進法に基づいて運用されています。
原則として次のような人が対象です:
- 原則18歳以上~原則45歳未満(ただし、自治体の判断により、知識と技能を有すれば65歳未満の例外を認めることがあります)
- 今後農業で自立した経営者になる意志と計画を持つ�人
- 農業を始めてから5年以内の者(あるいは直近で農業を開始しようとしている者)
認定の要件として、市町村に提出する「青年等就農計画」が次のような観点で適切と認められることが必要です。
- 計画の実現可能性(作付面積・販売計画・収支見込みなどが現実的)
- 自立した農業経営の見通しがある(5年以内に農業所得で生活できる想定)
- 地域との調和(農地の利用、水利などで地域に支障がない)
認定新規就農者になることで、次のような支援を受けられるようになります。
- 経営開始資金が年150万円(最長5年間)を無利子で交付されます。
- 準備資金(農業次世代人材投資資金)が、就農前の研修期間中にも年間最大150万円支援されます。
- 機械購入・施設整備などの補助が優先されます。
- 農地取得の許可が得やすくなります。
認定を受けるには、事前に地域の農業委員会や普及指導センターに相談するのが実務的に重要です。
一般人が農地を購入するために必要な手続き
「農業を本格的に始めたい」「地方に移住して家庭菜園をしたい」そのような思いから農地の購入を検討する方は少なくありません。しかし、農地法の規制のもとでは、一般の人が農地を取得するには、明確な条件と厳正な手続きを経る必要があります。
ここでは、農業経験のない一般の人が農地を買う際に必要な手続きを解説します。
就農計画の策定
農地の取得には、説得力のある営農計画書を作成する必要があります。具体的には次のような内容を含めるのが一般的です。
- 作付予定作物と作付面積
- 栽培方�法と年間スケジュール
- 農業に従事する人物の氏名・従事日数
- 収支計画(収穫量、販売見込額、経費など)
- 農機具や資材の調達方法
この計画が現実的でなければ、許可は下りません。農業未経験者であれば、地元の農業改良普及センターやJAなどと連携して、指導を受けながら作成するのが現実的です。
農業委員会の許可申請(農地法第3条許可)
農地を売買する場合には、農地法第3条に基づく許可が必須です。許可の申請先は、土地のある市町村の農業委員会です。
農業委員会に提出するための主な書類は次のとおりです。
- 農地法第3条許可申請書 農地の売買に関する基本情報を記載
- 土地の位置図 該当農地の場所を示す地図
- 営農計画書 どのように農業を行うかの詳細な計画
- 住民票・印鑑証明 申請者の本人確認書類
- 売買契約書案 農地の売買に関する同意内容(まだ未契約で可)
この他、必須ではありませんが、地元JAの意見書は就農意思を示す有力な補足資料になるので、積極的に提出を検討した方がいいでしょう。
申請後、農業委員会による現地調査が行われ、1ヶ月程度で審査・決定されます。
農業者としての登録・実態
購入後は名ばかりの農業者ではなく、実際に耕作を行う必要があります。
都道府県や市町村の農業委員会が「利用状況調査」を年1回以上行い、違反が確認されると文書指導→行政処分→所有権返還勧告と進みます。
そのため、許可を得た後にすぐに耕作しなければ、「農地の適正利用義務違反」として是正指導が入る可能性があるのです。
また、自治体によっては「農地利用状況報告書」の提出を義務づけているところもあります。農地は常に農業のために活用されている必要があり、怠れば農地を失うリスクもあります。
農地を購入する際の注意点
農地の取得は、一般的な宅地や山林の売買とは大きく異なります。法律の規制、地域の慣行、所有後の管理義務など、事前に理解しておかないと「こんなはずではなかった」という事態にもなりかねません。
ここでは、一般の人が農地を買う際に見落としてはいけない重要な注意点を詳しく解説します。
不動産登記を確認する
農地の売買において最も重要なのは、その土地が農地法上の「農地」であるかどうかを正確に把握することです。まずは登記簿で地目を確認し、「田」または「地目」と記載されているかをチェックします。
ただし、農地法では現況主義を採っているため、登記上は「宅地」でも、実際に耕作されていれば農地とみなされます。
そのため、現地での利用状況を確認することも欠かせません。「現況農地」であるかどうかは、市町村の農業委員会や地元の農業改良普及センターなどで確認できます。
また、不動産登記の際には、次の登記情報のチェックも併せて行ってください。
- 抵当権や根抵当権が設定されていないか
- 他人の通行権(地役権)が設定されていないか
- 共有名義になっていないか
万一、抵当権が残っていると後々トラブルになります。
抵当権が設定されている農地を売買する際は、抵当権者(多くの場合は金融機関)の許可を得る必要がある。
特に農業金融公庫や農協などの抵当権が設定されていることが多く、解除手続きが必要な場合もあります。
購入前に登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局で取得し、状況を精査しましょう。
「転用目的」は原則NG
農地法の原則において、農地は農業以外の目的で使うことはできません。農地を取得して次のような用途に転用することは、基本的に許可されません。
- 駐車場や資材置き場にしたい
- いずれ家を建てたい
- 別荘地として確保しておきたい
このような目的で取得することは、「偽装農業者」として指摘されるおそれがあります。買った後も継続的に耕作する義務があるという点を理解しておきましょう。
水利権・農業用水の管理関係を把握する
農地は、単に土地を持てば成り立つものではなく、「水利(すいり)」が極めて重要です。
「水利」とは、農業用水を適切に引き込み、利用し、管理するための仕組みや権利のことです。
水利は、単に水を使うことだけでなく、水を「いつ」「どこから」「どれだけ」引いて良いかという地域のルールや慣習も含みます。
このため、水利には個人の自由が及ばない側面があり、地域全体で協力しながら維持・運用していくものと考える必要があります。
特に水田の場合、地域の水路・水番・水利組合などとの関係を把握しておかないと、次のような問題が起こる可能性があります。
- 用水の使用料・管理費の支払い義務
- 水路清掃や水番の当番など、共同作業への参加
無断で水を引いた場合、水利権の侵害となることもあります。契約前には、必ず地元の水利組合や土地改良区に確認を取りましょう。
農業は地域社会との協調が不可欠です。地元の農家や水利組合、農業委員会との関係づくりを避け、独断的に購入を進めようとする姿勢は敬遠される傾向にあります。
地域と協力し、責任を持って農地を守る意思が必要です。
農業委員会の許可が得られるとは限らない
農地を取得するためには、農業委員会の許可が必要ですが、「申請すれば必ず通る」というわけではありません。農業経験のない人や新規就農を目指す人にとっては、ハードルが高くなることもあります。
特に新規就農者の場合は、「農業に真剣に取り組む意思」と「実際に取り組める体制」の両方があることを、面談や計画書を通じて丁寧に説明する必要があります。
そのうえで、例えば「就農計画が漠然としている」「平日に農作業時間を確保できない」「高齢で実行可能性に疑義あり」などの理由で不許可となるケースもあるのです。
どれだけ強い熱意があっても、実現性に欠けると判断されれば、許可が下りないことも十分にあり得ます。
つまり、「農業を始めたい」という気持ちだけでは、農地を購入することはできないのです。
無許可での売買は無効・罰則も
農地法第3条の許可を得ずに農地を売買(譲渡)しても、その取引は無効になります。
つまり、たとえ登記をしても法的な効力は認められず、買主がその農地を使用することもできません。
さらに、無許可で農地の権利移転や転用を行った場合には、農地法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった罰則が科される可能性があります。
軽い気持ちで進めてしまうと、思わぬ法的トラブルに発展する恐れがあるため、絶対に注意が必要です。
まとめ
農地の取得は、一般的な不動産購入とはまったく異なるルールと制限が設けられています。これらは農地法によって厳しく管理されており、農業従事者でなければ原則として所有することはできません。
ただし、農業経験がない人でも、実際に農業を始めるための研修や計画づくり、行政との連携を重ねることで、農地取得の可能性は十分に開かれています。
農地を買う前には、「なぜ買いたいのか」「どう活用するのか」を明確にし、その意図を農業委員会にしっかりと説明できるだけの準備を整えることが、成功の鍵となります。