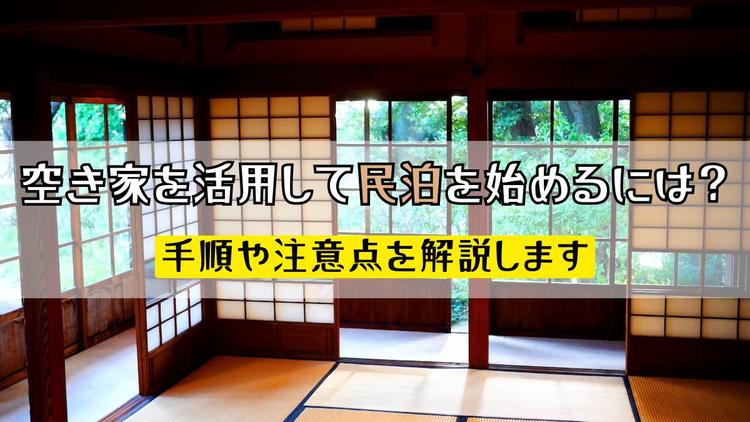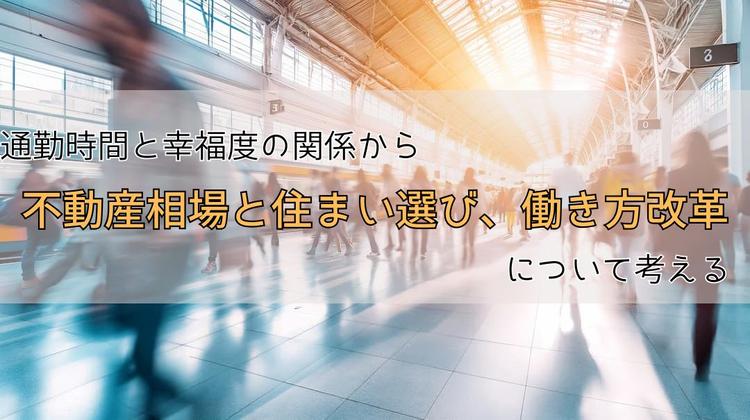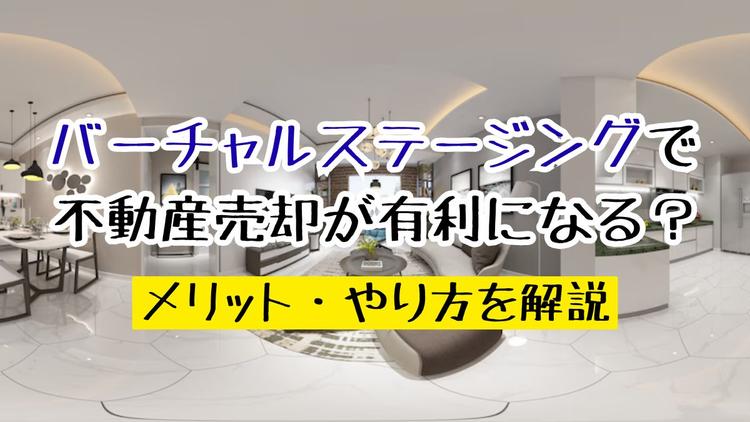空き家の活用方法の1つに、民泊があります。
空き家を民泊として活用すれば、賃料収入が得られたり、放置より維持管理できるなどのメリットがあります。
しかし、民泊にはトラブルになるなどのデメリットがあるうえ、開業には法律に基づいた手順を踏む必要があるので注意が必要です。
この記事では、民泊を始める手順やメリット・デメリット、民泊以外の活用方法などを分かりやすく解説します。
民泊とは
総務省の調査によれば、2023年10月1日時点での空き家は900万戸と、2018年に比べ51万戸増の過去最高を記録しています1。
団塊の世代の高齢化により今後も空き家は増加する見込みであり、自分が空き家の所有者になる可能性はゼロではありません。
空き家を所有する場合、放置はリスクが大きいため活用が重要です。
その空き家の活用方法の1つに民泊があります。
ここでは、民泊についての基本を押さえていきましょう。
一般の住宅を宿泊客に貸し出すサービス
民泊とは、個人が所有する住宅やその一部を、旅行者などの第三者に貸し出すサービスです。
ホテルや旅館と言った商業的な宿泊施設ではなく、個人の所有する居住用物件や投資用物件で行われるのが一般的で、民家を宿泊施設として提供することから民泊と呼ばれています。
民泊が注目される一つの要因が、近年の外国人観光客数の増加です。
日本政府観光局によると、2024年の訪日外国人旅行者数は3,687万人となり、これはコロナ禍以前最高となった2019年の3,188万人を上回る過去最高の人数となっています2。
外国人観光客数が増えたことで、ホテルなどの宿泊施設が不足し、その受け皿として注目が高まったのが民泊です。
とくに、外国人にとって民泊は特別なサービスではなく当たり前でもあることから、民泊需要が高まりを見せています。
また、近年は外国人だけでなく、国内でも農村体験など民泊需要が高まっていることもあり、個人で民泊を開業する人は増えているのです。
空き家を民泊として活用するための条件
空き家を民泊として活用するには、まずその住宅が「設備要件」と「居住要件」の2つを満たす必要があります。
設備要件としては、以下の4つの設備の設置が必要です。
- 台所
- 浴室
- 便所
- 洗面設備
なお、これらの設備は、必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一敷地内の建物であれば、一体的に使用する権限があり、かつ各建物の設備が使用可能な状態であれば、設置されているものとみなされます。
さらに、設備は一般的に求められている機能を有していれば十分とされています。
ただし、届出する住宅に設けられている必要があり、近隣の公衆浴場などを代わりにすることはできません。
一方、居住要件では対象となる住宅は次のいずれかに該当することが必要とされています。
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
- 入居者の募集��が行われている家屋
- 随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋
随時居住に供される家屋とは、生活の本拠としては使用されていないものの、所有者などが年に1回以上は利用する家屋のことを指します。
たとえば、転勤などで一時本拠を移している空き家や、相続し将来居住する予定の空き家、セカンドハウスや別荘などが、これに該当します。
これらの要件を満たしたうえで、民泊として活用するには法に基づく届け出が必要です。
以下では、具体的な民泊を始める手順を解説するので参考にしてください3。
空き家を活用して民泊を始める手順
2018年に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されたことにより、以前よりも民泊参入のハードルは低くなっています。
とはいえ、民泊は必要な手続きを踏まなければ違法民泊となるので、法に基づいた届出は許可を得て開業するようにしましょう。
民泊を始める場合、以下の3つのいずれかに基づいた手続きが必要です。
- 住宅宿泊事業法
- 旅館業法
- 国家戦略特別区域法
以下でそれぞれ詳しくみていきましょう。
住宅宿泊事業法に基づく場合
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて民泊を行う場合、都道府県知事などに届出を行うだけで民泊をスタートできます。
他の2つの方法よりもハードルが低く、一般的に民泊を行う場合に選ばれる方法です。
住宅宿泊事業法に基づく場合、宿泊者の衛生の確保のために利用者1人当たり3.3㎡以上の居室面積の確保と、定期的な清掃の義務が求められます。
さらに、安全確保のための非常用照明器具や、避難経路の設置なども必要です。
ただし、住宅の延長としての運営が必要となり、事業用不動産での運営は認められません。
また、営業日数には年間180日未満という制限があるので注意しましょう。
旅館業法に基づく場合
旅館業法とは、宿泊サービスに対するルールを定めた法律です。
旅館業法に基づいて民泊を行う場合、簡易宿所営業という形態になるのが一般的です。
簡易宿所とは、宿泊する場所を他人数で共有する構造・設備を主とする施設で、宿泊料を受けて営業する下宿営業以外のものです。
たとえば、山小屋やペンションなどが簡易宿泊営業に該当します。
簡易宿所とみなされるには、1室あたり33㎡以上(10人未満では3.3㎡×人数)の広さが必要になります。
また、衛生の確保として換気や採光、照明や排水設備の完備などの条件も満たす必要があるので注意しましょう。
簡易宿所として営業できれば、年間の営業日数に制限がなく、通年での営業が可能です。
ただし、設備面・構造面・周辺環境など、クリアしなければならない要件が多いため、許可取得のハードルはやや高いといえるでしょう。
国家戦略特別区域法に基づく場合
国家戦略特別区域法とは、国際競争力を強化し、国�際的な経済拠点となる地域を形成することを目的とした法律です。
この法律により、一定の地域が「国家戦略特区」に指定され、そこで事業を行う際には、法で定められた規制の特例措置を活用できるようになります。
この国家戦略特別区域法に基づく場合、「特区民泊」として営業することになります。
特区民泊では、1室あたり25㎡以上の居住面積が必要となり、宿泊日数も2泊3日以上という制限があります。
ただし、年間の営業日数の制限はないため通年での営業が可能です。
特区民泊は、運営可能な地域が自治体ごとに制限されており、開業には自治体の認定が必要です。
自治体によっては特区に認められていない場合もあるので、開業できる地域は限定的となります。
空き家を活用して民泊を始めるメリット
空き家を活用して民泊を始めるメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
- 宿泊料を得られる
- コストを抑えやすい
- 空き家のままにしておくより維持管理しやすくなる
それぞれ見ていきましょう。
宿泊料を得られる
民泊を経営すれば、利用に応じて宿泊料を得られます。
仮に、1泊1万円で貸し出し年間180日営業すれば、最大で180万円の収入が見込めます。
空き家は活用せずに所有し続けても、固定資産税や管理費などの負担が生じます。
民泊の宿泊料を得られれば、これらの費用を賄うこともできるでしょう。
コストを抑えやすい
すでに所有している物件を活用するので、新しく物件を購入するコストがかかりません。
賃貸運営では不動産購入コストで初期費用がかかりますが、その点初期費用を大きく抑えて運営をスタートでき、収支も安定させやすくなります。
ただし、物件の状態によってはリフォームなどの初期費用がかかってくるので、あらかじめ初期費用をシミュレーションしておくことが大切です。
空き家のままにしておくより維持管理しやすくなる
空き家を活用しない場合でも、維持管理は必要です。
空き家を放置していると建物の劣化が進み、将来活用や売却しようと考えたときに修繕費が余計にかかる、状態が悪くて売れないとなりかねません。
また、空き家を放置することで倒壊や犯罪リスクが高まる点にも注意が必要です。
仮に、適切に管理せずに倒壊すると、近隣に被害を出し損害賠償請求される恐れがあります。
倒壊しなくても、草木が生い茂る・不法投棄されるなどで近隣からクレームが来る可能性もあるでしょう。
さらに、空き家を放棄していると自治体から「特定空き家」に指定されるリスクもあるのです。
「特定空き家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が解除されるなどのデメリットが生じる。
これらのリスクを避けるには、空き家を適切に管理する必要があります。
定期的に空き家を訪れて清掃や換気・見回り・修繕などを行う必要があり、管理の負担がかかります。
その点、民泊として活用すれば日常的に維持管理をすることになるので、劣化を防ぐことにつながるでしょう。
▼関連記事:空き家は放置すると劣化が早い!必要なメンテナンスを解説します
空き家を活用して民泊を始めるデメリットと注意点
空き家を民泊にするデメリットや注意点としては、以下の3つが挙げられます。
- 営業日数に上限がある
- 海外観光客の利用が多くそれぞれの文化への理解が求められる
- 近隣住民とトラブルになる可能性がある
それぞれ見ていきましょう。
営業日数に上限がある
民泊新法にもとづいて民泊を始める場合、年間の営業日数は180日という制限が設けられます。
年間を通して営業できるわけではないので、収益も大きくしにくい点には注意が必要です。
観光シーズンは民泊、それ以外のシーズンは賃貸や自分で利用するなど、使わないときの活用方法も検討しておくようにしましょう。
なお、旅館業法・国家戦略特別区域法に基づく民泊では、年間の営業日数の上限はありません。
民泊新法よりも参入のハードルは高いですが、収益化を狙うなら検討するのも1つの方法です。
海外観光客の利用が多くそれぞれの文化への理解が求められる
民泊の主な利用者は、海外観光客です。
そのため、言語や文化の違いによるトラブルが発生するリスクが高い点には注意しなければなりません。
たとえば、日本語で記載した宿泊ルールを読めずにルールを守らない、備品の使い方の違いで壊されるなどはよくあります。
日本人にとっては当たり前のマナーも、文化や習慣が異なれば理解してもらえないものです。
あらかじめ、利用が見込まれる国の文化や言語に対してある程度理解しておくと、トラブルを避けやすくなるでしょう。
近隣住民とトラブルになる可能性がある
宿泊客が��ルールを守らず夜中に騒いだり、大量のゴミを周囲に放置するなどで近隣住民とトラブルになることもあります。
近隣とトラブルにならないように宿泊客がルールを守るための対策を行うだけでなく、民泊開業前に近隣に挨拶するなどで一定の理解を得られるようにしておきましょう。
民泊以外で空き家を活用する方法
空き家の活用方法は民泊だけではありません。
民泊は、国籍問わず不特定多数の宿泊客が家を利用することから、抵抗感があるという方もいるでしょう。
ここでは、民泊以外の空き家の活用方法として「自分で住む」「賃貸に出す」「売却する」の3つを解説します。
自分で住む
最も簡単な活用方法が、自分で住むことでしょう。
自分で住めば日常的な維持管理は住みながら行えます。
固定資産税などの負担はありますが、それまでが賃貸暮らしであれば賃料の負担が軽減するので、トータルの負担は軽くなる可能性があるでしょう。
ただし、空き家の状態によっては住み始める前に大規模なリフォームが必要となるため、事前に初期費用をシミュレーションしておくことが大切です。
賃貸に出す
自分で住むのが難しい場合、第三者に賃貸として貸し出す方法もあります。
賃貸であれば事前に入居者審査を行うため、民泊のように不特定多数が宿泊する不安はなくなります。
入居者がいる限り賃料収入があるので、安定した収入も見込めるでしょう。
しかし、賃貸として需要があるかは空き家の立地や周辺環境にも大きく左右されるため、事前にニーズを徹底的に調査することが大切です。
また、賃貸運営前にリフォームやリノベーションが必要な場合もあるので、初期費用がある程度かかる点には注意しましょう。
売却する
活用が難しいなら、早い段階で売却して手放すことをおすすめします。
使わない空き家を所有しつづけても税金や管理費の負担が生じ続け、さらに放置に��はリスクもあります。
売却することで、これらの負担やリスクを避けることが可能です。
空き家を売却する場合、建物付きで売る・更地にして売却する方法が検討できます。
どちらが適しているかは建物の状態などによって異なるので、まずは不動産会社に相談したうえで売却方針を決めることをおすすめします。
できるだけ多くの不動産会社の査定を比較し、信頼できる不動産会社を選ぶようにしましょう。
また、築年数が古いなど売りにくい空き家の場合、買取を視野に入れた方がスムーズな売却が期待できます。
売却方針に悩む場合は、仲介・買取両方の査定を受けて検討するのも1つの方法です。
イエウリでは、仲介・買取両方の一括査定に対応しています。
査定時には不動産会社に個人情報が伝わらないので、査定後に営業電話に悩まされる心配もありません。
大手から中小まで数多くの不動産会社の査定を簡単に比較できるので、売却を検討しているならお気軽にご利用ください。
複数社の査定で適正価格をチェック
イエウリ の不動産査定はこちら
まとめ
空き家を民泊として活用することで、宿泊料を得られ日常的な管理もできるというメリットがあります。
しかし、民泊は海外観光客利用が多く言語や文化の違いでトラブルになったり、近隣住民からクレームがきたりする恐れがある点には注意が必要です。
また、民泊として活用するには法律に基づいて届出や許可が必要になる点も覚えておきましょう。